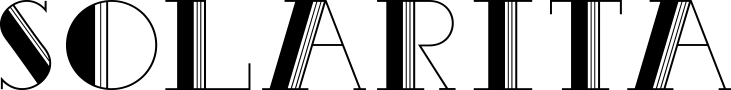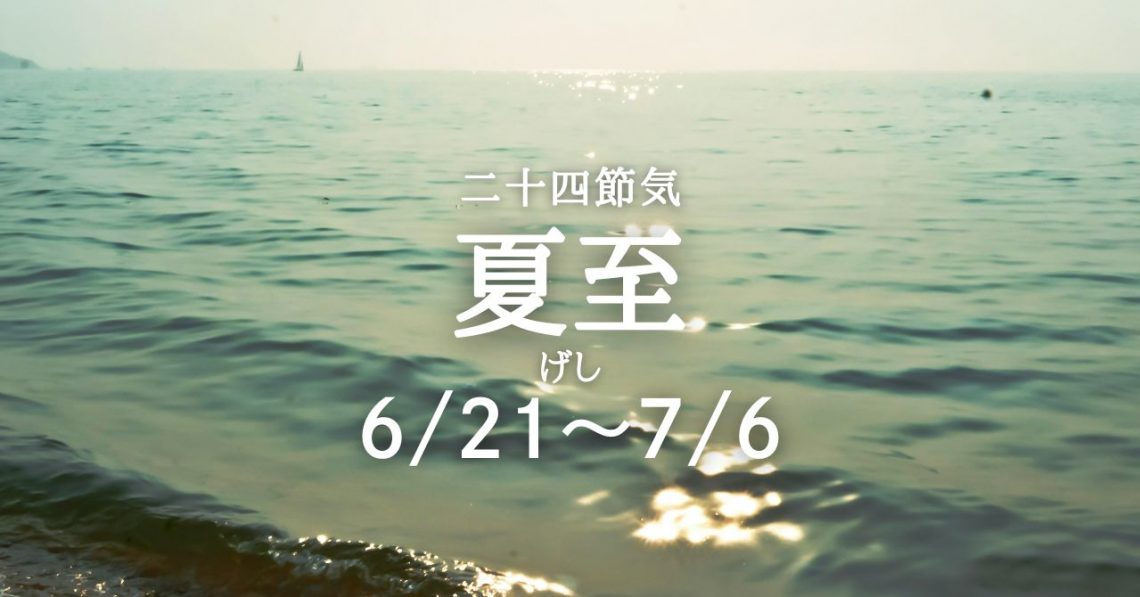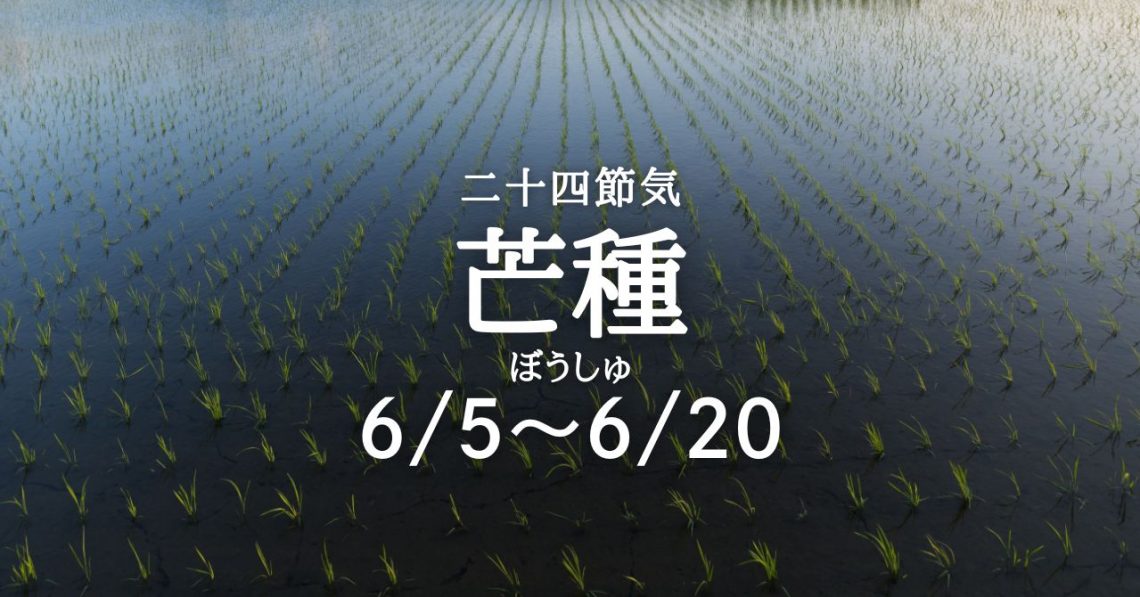-
立秋(りっしゅう)の季節に入ります(8/7-8/22)
二十四節気で立秋(りっしゅう)を迎えます。暦の上では秋へと季節が変わります。 二十四節気で「立秋」を迎えました。そう、暦の上では秋に入ったのです。真夏日が続いているので「もう秋!?」感が強いですが、考えてみれば毎年毎年、…
-
大暑(たいしょ)の季節に入ります(7/22-8/6)
二十四節気で「大暑(たいしょ)」の季節。暦の上では最も暑い時期の到来となります。 大暑。その名称の通り、日本で最も暑い季節がやってきます。夏至→小暑→大暑の流れで「ニッポンの夏」が勢いを増しています。ただ、実際に最も暑い…
-
小暑(しょうしょ)の季節に入ります(7/6-7/21)
二十四節気で「小暑(しょうしょ)」に。梅雨が明けるとギラリと暑い「ニッポンの夏」を迎えます。 小暑の季節です。言葉の通りかあるいは言葉と裏腹なのか、「小さい暑さ」という表現では追いつかないほど暑さが本格化していく時期です…
-
夏至(げし)の季節に入ります(6/21-7/6)
二十四節気で「夏至(げし)」を迎えます。太陽が最も強くなり、陰陽の「陽」が極まる季節です。 夏至は一年で最も昼の時間が長くなる日です。そしてあたりまえのことですが、夜が最も短くなる日でもあります。このことから、夏至は太陽…
-
芒種(ぼうしゅ)の季節に入ります(6/5-6/20)
二十四節気で「芒種」に入ります。運気は外へ、外へと向かう季節です。 芒種の芒は、イネ科植物の穂先にある針のような突起のことで、「のぎ」と読みます。6月5日から始まる「芒種」の季節はこの芒のある穀物の種を撒く時期で、田植え…
-
「小満」の季節です(5/21-6/4)
二十四節気で「小満」に入ります。万物が世界に満ちる勢いのある季節です。 二十四節気では5月21日より「小満(しょうまん)」の季節に入ります。江戸時代に編纂された暦の解説書『暦便覧』では、小満の季節を「万物盈満(えいまん)…
-
「立夏」の季節です(5/5-5/20)
二十四節気で「立夏」に入りました。5月5日より暦の上で夏となります。 多くの人の実感としては「もう夏!?」といったところだと思います。そもそも二十四節気は1年を4つの季節に分けて、それぞれをさらに6つの期間に分けたもの(…
-
穀雨(こくう)の季節です(4/20-5/4)
二十四節気では、万物が生き生きと立ち上がる「清明(せいめい)」の季節に入りました。 清らかで明るい。この文字を見るだけでも清々しく晴れやかな気持ちになれそうですね。もともとは「清澄明潔」という四字熟語の略語だとか。春の朗…
-
「春分」の季節です(3/20-4/3)
二十四節気では、太陽が生まれ変わる春分(しゅんぶん)の季節に入りました。 今年の春分の日は3月20日です。春分の日には、太陽が真東からの上って真西に沈み、昼と夜の長さが同じとなります。 そして二十四節気の春分の季節は3月…
-
清明(せいめい)の季節です(4/4-4/19)
二十四節気では、万物が生き生きと立ち上がる「清明(せいめい)」の季節に入りました。 清らかで明るい。この文字を見るだけでも清々しく晴れやかな気持ちになれそうですね。もともとは「清澄明潔」という四字熟語の略語だとか。春の朗…