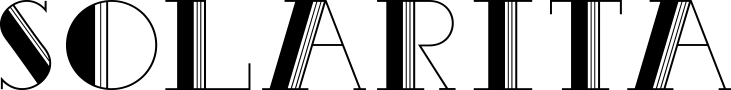-
涼風至(すずかぜいたる)5日間です(8/7-8/11)
二十四節気「立秋」の初候は七十二候「涼風至(すずかぜいたる)」の5日間となります。 二十四節気で「立秋」を迎えると同時に、七十二候は「涼風至」となります。季節は少しずつ秋に向かい、涼しげな風が吹く時季という意味。いま一年…
-
大雨時行 (たいう ときどきふる)、5日間です(8/2-8/6)
二十四節気「大暑」の末候は七十二候「大雨時行 (たいうときどきふる)」の5日間となります。 「大暑」の季節も終盤となっています。実際はこれからが本番という感じですが、暦の上では今がもっとも暑い季節であり、その終盤を迎えて…
-
土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし) の五日間です(7/28-8/1)
二十四節気「大暑」の次候は七十二候「土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし) 」の5日間となります。 暦の上で一年で最も暑い季節、二十四節気で大暑を迎えています。大暑の次候として土潤溽暑の時季が巡ってくるのですが、その文字面…
-
桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ) の6日間です(7/22-7/27)
二十四節気「大暑」の初候は七十二候「桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ)」の6日間となります。 暦の上で一年で最も暑い季節、二十四節気で「大暑」を迎えると同時に、七十二候では「桐始結花」の季節に入ります。桐の花が開くのは…
-
蓮始開(はす はじめてひらく)の5日間です(7/12-7/16)
二十四節気「小暑」の次候は七十二候「蓮始開(はす はじめてひらく)」の5日間となります。 七十二候で「蓮始開(はすはじめてひらく)」という時季に入ります。言葉の通り、蓮の花が咲き始める時です。蓮の花はよく知られているよう…
-
温風至(あつかぜいたる)の5日間です(7/7-7/11)
二十四節気「小暑」の初候は七十二候「温風至(あつかぜいたる)」の5日間となります。 温風とは熱を帯びた南風のこと。この時期には梅雨が明ける地方も出てきて、亜熱帯から吹き込む風が日本列島を包み込む季節に入ろうとしています。…
-
半夏生(はんげ しょうず)の6日間です(7/1-7/6)
二十四節気「夏至」の末候は七十二候「半夏生(はんげ しょうず)」の6日間となります。 半夏とはある薬草のことを指します。「烏柄勺(からすびしゃく)」という植物で、その球根の皮を取り乾燥したものが漢方薬の半夏。吐き気や嘔吐…
-
菖蒲華(あやめ はなさく)の5日間です(6/26-6/30)
二十四節気「夏至」の次候は七十二候「菖蒲華(あやめ はなさ く」の5日間となります。 菖蒲が花を咲かせる頃です。ここでは菖蒲はアヤメと読みますが、この漢字自体はショウブとも読みます。また、「何れ菖蒲か杜若(いずれあやめか…
-
乃東枯(なつかれくさ かるる)の5日間です(6/21-6/25)
二十四節気「夏至」の初候は七十二候「乃東枯(なつかれくさかるる)」の5日間となります。 乃東枯は二十四節気の夏至とともに始まります。一年で昼間が最も長く、それゆえに太陽の力が最も強まる時季です。 乃東とは「夏枯草(かこそ…
-
梅子黄(うめのみ きばむ)の5日間です(6/16-6/20)
二十四節気「芒種」の末候は七十二候梅子黄(うめのみきばむ)の5日間となります。 全国的に梅雨入りとなっています。梅雨に入ることを入梅(にゅうばい)と呼びますが、「梅の実が熟す頃の雨」ということから「梅雨」になったとも言わ…