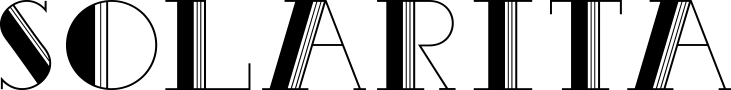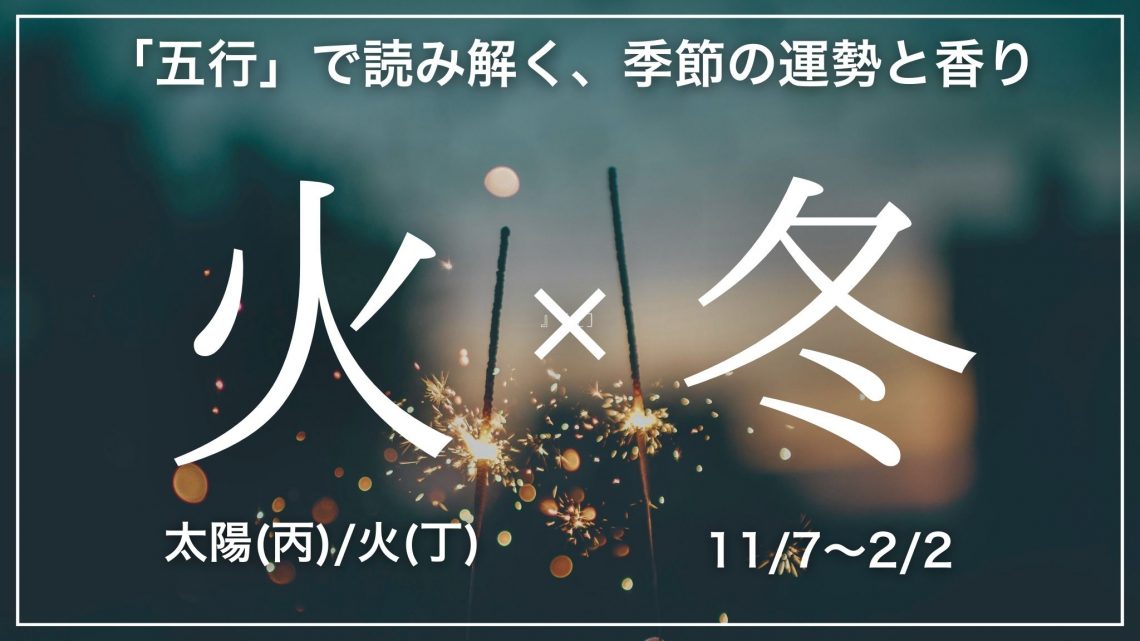-
「火」タイプが、冬に取り入れるべき五行とは?
この記事は「火」タイプ、四柱推命では太陽(丙)、火(丁)タイプの方々に向けたものです。五行では「火」タイプとなるあなたが、暦の上での冬(11/7〜2/2)の季節を健やかに前進するための秘訣を説明しています。 自分の五行が…
-
「木」タイプが冬に取り入れるべき五行とは?
この記事は「木」タイプ、四柱推命では樹木(甲)、草花(乙)タイプの方々に向けたものです。五行では「木」タイプとなるあなたが、暦の上での冬(11/7〜2/2)の季節を健やかに前進するための秘訣を説明しています。 自分の五行…